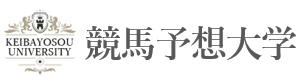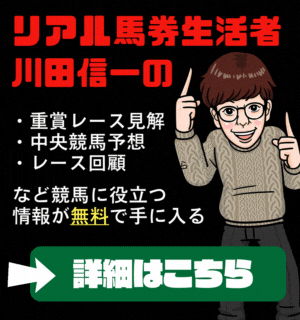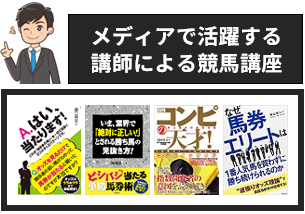- 2024年3月31日(日)阪神12R:陽春ステークス(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年3月30日
- 2024年3月31日(日)阪神10R:キタサンブラックC(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年3月30日
- 2024年3月31日(日)阪神9R:バイオレットS(2024)【勝ち組の出馬表】 - 2024年3月30日
- 2024年3月31日(日)阪神8R:4歳以上1000万円以下【勝ち組の出馬表】 - 2024年3月30日
- 2024年3月31日(日)阪神7R:4歳以上1000万円以下【勝ち組の出馬表】 - 2024年3月30日
こんにちは。編集部のJです。
日本の競馬ファンに、「今、日本の競走馬に最も勝ってほしい海外のレースは?」という質問をしたら、間違いなく第一位になるのが、フランスの凱旋門賞でしょう。
10月の最初の日曜日に行われる凱旋門賞は、ヨーロッパ競馬の最高峰ともいえる大一番。近年は日本からの挑戦も相次ぎ、2016年に始まったJRAの海外馬券発売も凱旋門賞がその栄えある最初のレースになりました。レースの模様は、日本でも地上波で生中継されるほどです。
今回はそんな凱旋門賞についてと、馬券攻略のためのレース傾向を探っていきましょう。
目次
凱旋門賞の基礎知識

凱旋門賞の歴史
まずは凱旋門賞の歴史を紐解いていきましょう。
凱旋門賞の創設は1920年。第一次世界大戦からの復興を目指すフランスで誕生しました。創設の目的は、国際競走でフランス産馬の優秀さを証明すること。当時フランスでは、すでに3歳馬による春のパリ大賞(1863年に創設)が国際競走として成功を収めていました。
また、秋にも古馬混合のコンセイユミュニシパル賞(市議会賞)という競走がありましたが、これは別定重量であったため、馬齢重量で争われる真のチャンピオン決定戦としてつくられたのが凱旋門賞でした。
しかし、現在のような成功がいきなりあった訳ではありません。創設2年目に賞金がパリ大賞と同等レベルになったにも関わらず、当時トップレベルにあったイギリスからの一流馬の参戦がなく、しばらくして第二次世界大戦が勃発。凱旋門賞も1939、40年の二年間が開催中止になり、43、44年は戦火の影響を受けたロンシャン競馬場に替わり、ルトランブレー競馬場での代替開催となりました。
そんな凱旋門賞の価値を高めるきっかけとなったのが、1949年に国営宝くじを賞金の原資としたことです。賞金が前年の5倍近くまで跳ね上がったことで、ヨーロッパ最高賞金のレースとなり、ヨーロッパ以外からの出走馬も増加。さらに、その後にリボー、シーバード、ミルリーフといった名馬たちが優勝馬として名前を刻んだことで、世界のホースマンが目標にするレースへと成長を遂げたのです。
凱旋門賞の賞金・売上
2018年の凱旋門賞の賞金総額は、500万ユーロ。およそ6憶5000万円。1着賞金は285万7000ユーロ(およそ3憶7000万円)になります。
これは、フランス国内のレースはもちろんのこと、ヨーロッパ全体でも最も高い賞金です。フランスで賞金が2番目に高いフランスダービーの賞金総額が150万ユーロですから、凱旋門賞の賞金がいかに飛び抜けているかがわかるでしょう。
次に凱旋門賞の売上を見ていきます。
2016年の凱旋門賞の売上は、およそ6200万ユーロ(およそ81億円)です。売上の70%以上にあたる4500万ユーロ(およそ59憶円)が、フランス国外での売上だったと言われています。その中で一番売上に貢献していたのが、実は日本です。マカヒキが出走したこの年の凱旋門賞が、初めての海外馬券発売ということもあり、42憶円近い売上をたたき出しました。
凱旋門賞の観客数
2016年の凱旋門賞の観客数は、例年よりやや少な目のおよそ4万2000人でした。16年と翌17年はロンシャン競馬場が改修工事中でしたので、シャンティイ競馬場での代替開催だったことが、例年より観客数が少なかった原因です。ロンシャン競馬場では例年6万人近い観客が集まります。
フランスの競馬場には、東京競馬場ほど収容人数がある競馬場がないため、凱旋門賞でも10万人を超えるような観客数になることはありません。
凱旋門賞のレコード
凱旋門賞のレコードタイムは、ファウンドが記録した 2分23秒61 です。シャンティイ競馬場での代替開催だった2016年につくられました。
ロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞で最も速いタイムは、デインドリームが勝った2011年の2分24秒49。デインドリーム以前のレコードだった1997年パントレセレブルの2分24秒6を含めて、 2分25秒を切るタイムはまだ3回しか記録されていません。
凱旋門賞の一次登録について
凱旋門賞の一次登録は5月に行われ、その時点での登録料はおよそ100万円です。一次登録をしてない馬が出走するためには、追加登録料としておよそ1500万円 を払わなければならなくなります。
そんな事情もあり、多くの陣営は五ヶ月先の本番を見越して、出走が見込める多くの実力馬たちを登録してくるため、一次登録は100頭を超えることもあります。
凱旋門賞の出走条件とは!?
凱旋門賞の出走条件は、3歳以上の牡馬および牝馬。凱旋門賞は優秀な繁殖馬選定のための競走ということで、セン馬の出走が認められていません。
過去には20頭を超える出走頭数も記録しましたが、現在は安全性を考慮して、出走頭数を20頭に制限しています。
凱旋門賞への日本馬の挑戦の歴史
凱旋門挑戦のパイオニアとなったのは、スピードシンボリです。今からおよそ半世紀近く前の1969年にヨーロッパ遠征を敢行。遠征3戦目として臨んだ凱旋門賞でしたが、着外(当時は11着以下をすべて着外扱い)に終わりました。
スピードシンボリの挑戦から3年後の72年に挑んだメジロムサシもヨーロッパのレベルの高さにまったく歯が立たず、18着に敗れています。
さらに14年の時を経て、86年にはシリウスシンボリが挑戦をしています。85年の日本ダービーを制した後に、3年に跨る長期のヨーロッパ遠征を行ったシリウスシンボリでしたが、凱旋門賞の14着などヨーロッパでの成績は14戦全敗。当時はダービー馬でもヨーロッパで勝利を挙げることが難しい時代でした。
98年に日本馬が初めてヨーロッパのG1を制覇した翌99年、エルコンドルパサーがフランスへ向かいます。サンクルー大賞(G1)に優勝して、日本馬がヨーロッパの2400mでも通用することを証明しました。凱旋門賞での快挙達成はなりませんでしたが、果敢に先頭に立ってレースを引っ張り、モンジューからクビ差の2着。この善戦で日本馬による凱旋門賞制覇という夢が現実味を帯びてきました。
2000年代以降は日本馬が海外のレースに出走することも増えて、凱旋門賞にも毎年のように日本から挑戦するようになります。
そして、日本中の期待が最も高まったのが、無敗の三冠馬ディープインパクトが挑んだ2006年でした。1番人気として出走したディープインパクトでしたが、「飛ぶような走り」と評された本来の姿は見られずに3位入線。後に治療のために投与された薬が発端となる禁止薬物が検出されたことで、失格処分になってしました。
その後も、2010年にナカヤマフェスタがワークフォースとの接戦の末にアタマ差の2着に惜敗。2頭目の三冠馬による挑戦となったオルフェーヴルも、12、13年でともに1番人気になるも、12年はいったん先頭に出ながらソレミアに差し返されて2着。翌13年も最強牝馬トレヴの前に2着に敗れ去りました。
日本馬による凱旋門賞への挑戦は、2017年までにのべ22頭を数えますが、ここまで4度の2着が最高で、まだその栄光を掴んだ馬は現れていません。
| 年度 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|
| 2017年 | サトノダイヤモンド | 15着 |
| サトノノブレス | 16着 | |
| 2016年 | マカヒキ | 14着 |
| 2014年 | ハープスター | 6着 |
| ジャスタウェイ | 8着 | |
| ゴールドシップ | 14着 | |
| 2013年 | オルフェーヴル | 2着 |
| キズナ | 4着 | |
| 2012年 | オルフェーヴル | 2着 |
| アヴェンティーノ | 17着 | |
| 2011年 | ヒルノダムール | 10着 |
| ナカヤマフェスタ | 11着 | |
| 2010年 | ナカヤマフェスタ | 2着 |
| ヴィクトワールピサ | 7着 | |
| 2008年 | メイショウサムソン | 10着 |
| 2006年 | ディープインパクト | 失格 |
| 2004年 | タップダンスシチー | 17着 |
| 2002年 | マンハッタンカフェ | 13着 |
| 1999年 | エルコンドルパサー | 2着 |
| 1986年 | シリウスシンボリ | 14着 |
| 1972年 | メジロムサシ | 18着 |
| 1969年 | スピードシンボリ | 着外 |
凱旋門賞の攻略情報
ここでは馬券攻略の観点から、過去の凱旋門賞のデータを中心に、その傾向をつかんでいきましょう。
凱旋門賞は荒れやすい!?凱旋門賞のレース波乱度
2008~17年の過去10年を見ると、1番人気は3勝。ヨーロッパのチャンピオンを決める位置づけにしては、1番人気の信頼度がやや低い印象ですが、2着も2回あって、連対率は50%とまずまずの数字です。3着の1回を含めた複勝率は60%あり、3連系の馬券で勝負をするのであれば、押さえておきたいところです。
一方で人気のない馬が台頭するケースも十分に考えておかなければならないでしょう。なんと、10番人気以下が過去10年でも2勝、2着も3回もあるのです。毎年20頭近い出走馬が集まるだけに、順当に収まる年ばかりではありません。
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1人気 | 8人気 | 3人気 |
| 2016年 | 3人気 | 9人気 | 8人気 |
| 2015年 | 3人気 | 5人気 | 2人気 |
| 2014年 | 7人気 | 11人気 | 1人気 |
| 2013年 | 2人気 | 1人気 | 4人気 |
| 2012年 | 12人気 | 1人気 | 6人気 |
| 2011年 | 11人気 | 15人気 | 8人気 |
| 2010年 | 4人気 | 12人気 | 8人気 |
| 2009年 | 1人気 | 7人気 | 6人気 |
| 2008年 | 1人気 | 4人気 | 5人気・13人気 |
凱旋門賞の斤量の決め方・有利な斤量は!?
凱旋門賞の斤量は3歳牡馬が56.5キロ、4歳以上牡馬が59.5キロ。牝馬はそれぞれ1.5キロ軽くなり、3歳牝馬が55キロ、4歳以上牝馬が58キロになります。
2008~17年の過去10年の優勝馬の性齢は以下の表のとおり。
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 牝3 | 牡4 | 牡4 |
| 2016年 | 牝4 | 牡4 | 牡4 |
| 2015年 | 牡3 | 牡5 | 牡3 |
| 2014年 | 牝4 | 牡4 | 牝3 |
| 2013年 | 牝3 | 牡5 | 牡3 |
| 2012年 | 牝4 | 牡4 | 牡3 |
| 2011年 | 牝3 | 牝3 | 牝4 |
| 2010年 | 牡3 | 牡4 | 牝3 |
| 2009年 | 牡3 | 牡6 | 牡3 |
| 2008年 | 牝3 | 牡5 | 牡4・牡5 |
※2008年は3着が同着
優勝馬は3歳牝馬の4頭が最も多く、3歳牡馬と4歳牝馬の3頭が続いて、4歳牡馬の優勝はゼロ。5歳以上にいたっては牡馬、牝馬を問わず勝てていません。
そして、ここ10年で顕著なのが牝馬の活躍です。この10年で7頭も勝利しています。
ただし、斤量は、2017年に改定されていて、それ以前は3歳牡馬が56キロ、3歳牝馬が54.5キロでした。これはヨーロッパ全体で改定されたもので、凱旋門賞の斤量だけが変更に訳ではありません。今後も3歳、そして牝馬に有利な流れが続くのか、注目していく必要があるでしょう。
凱旋門賞で有利な脚質は!?
2008~17年の過去10年の優勝馬の脚質は、「差し」が6勝、「先行」が4勝です。「逃げ」と「追い込み」のような極端な戦法は決まりづらいデータが出ています。
逃げが決まらないのは、多くの年で逃げるのが、有力馬のサポート役を務めるペースメーカーであることが大きいでしょう。
また、凱旋門賞開催時には仮柵が取り除かれて、馬場の良い内を通る馬が有利になるため、大外からの追い込みは決まりづらくなっていました。
しかし、多頭数ということもあって追い込み馬が大外を回らざるを得ない状況は、今後変わってくるかもしれません。2018年4月にリニューアルオープンしたパリロンシャン競馬場では、新たにオープンストレッチが採用されているからです。
オープンストレッチとは、直線で仮柵を内側に移動させてコース幅を広げるもの。直線で馬群がばらけることが狙いです。差し、追い込みの馬たちにとっては、新たに生まれる内のスペースを突くことが可能になりました。
凱旋門賞で内枠・外枠のどちらが有利!?
2008~17年の過去10年で連対率が高い枠順は、3番が3回(1着1回、2着2回)で一位。続くのが1番(1着1回、2着1回)、2番(1着2回)、6番(1着2回)、11番(2着2回)の2回です。
脚質のところでも書いたように、仮柵の取れたところを通れる内側が有利というデータになりました。ただし、パリロンシャン競馬場の新たなオープンストレッチ導入が、今後どのような影響をもたらすか、脚質同様に注意が必要でしょう。
一方で、出走馬が20頭近くなることが多いこともあって、大外枠は不利といわれています。しかし、2008~17年の10年だけでも2012年にオルフェーヴルが18番枠から2着になり、2009年は19番枠からキャヴァルリーマンが3着に入っています。まったく勝負にならないというわけではなさそうです。
凱旋門賞を日本馬が勝てない理由
アウェイでの戦いになる海外のレースは、長距離の輸送や環境の変化など、厳しい条件下になるのですから、勝利することは容易ではありません。それでも日本馬は香港やドバイ、そして欧米でもG1で勝利を挙げてきました。
では、なぜ凱旋門賞を勝つことができていないのか? 考えられる一番の要因は、凱旋門賞がシーズンのハイライトになるチャンピオン決定戦だからではないでしょうか。
例えば、ドバイの芝のレースでは、強敵となるヨーロッパ馬がシーズン開幕前になります。12月の香港国際競走ではヨーロッパ馬はシーズン終了後の遠征になり、香港馬はシーズンが始まって3ヶ月しか経っていない時期の開催です。
それに対して凱旋門賞は、シーズンのハイライトとして、ヨーロッパの実力馬たちが体調をピークに持ってくるわけですから、日本馬がほかの海外のG1を勝つよりも至難の業です。
凱旋門賞に強い国とは!?
2017年まで96回行われてきた凱旋門賞の優勝馬を調教国で見ると、地元フランスの66勝が最多で、以下はイギリスの15勝、アイルランドの7勝、イタリアの6勝、ドイツの2勝と続きます。
注目はまだヨーロッパ以外の国から優勝馬が出ていない点です。果たして日本がヨーロッパ以外で最初に凱旋門賞を制することができるのでしょうか。
[まとめ]ヨーロッパ最高峰のレース だからこそ日本からも挑戦する価値がある

日本の競馬界のみならず、世界のホースマンが凱旋門賞を目指す理由がお分かりいただけたかと思います。
今は日本国内でも海外馬券の購入ができるようになり、競馬ファンにとっても凱旋門賞が以前よりも身近なものになってきたのを感じます。
ここでご紹介したレース傾向をご参考に、皆さんも馬券というかたちで、日本馬の凱旋門賞制覇という悲願達成を、応援してみてはいかがでしょうか。